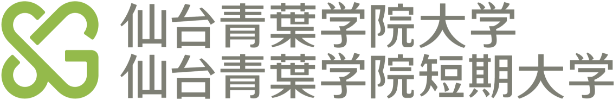言語聴覚士とは?仕事内容や一日の流れ、仕事の魅力・やりがいを紹介
今後の日本は、今以上に高齢化が進行し、高齢者に対するリハビリテーションの需要は増すと予想されています。そこで重要になってくるのが、リハビリを専門とする国家資格を保有する医療従事者です。
言語聴覚士とは、言語・聴覚・発語・嚥下(食べ物を咀嚼して飲み込むこと)に関するリハビリテーションを専門とする医療の国家資格です。
そこで本記事では、言語聴覚士の仕事内容や就職先、一日の仕事の流れなどをご紹介します。記事後半では言語聴覚士の魅力・やりがいや、向いている人の特徴、将来性などを幅広く解説するので、言語聴覚士を目指している方はぜひ参考にしてみてください。
言語聴覚士とは
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)とは、「話す・聞く・食べる」に特化したリハビリテーションの国家資格を持つ職業です。病気やけがで言語・聴覚・発語・嚥下に障害を抱えた患者さんに対し、社会復帰をサポートして自分らしい生活を取り戻せるように支援・サポートします。
専門学校・短期大学・4年制大学にて法律に定められた教育課程を修了した後に、国家試験に合格すると資格を得られます。言語聴覚士が活躍できる場所は、病院や診療所、通所リハビリテーション、訪問介護ステーション、リハビリテーション支援センターなどのリハビリ施設はもちろん、保健所や教育施設、研究施設などさまざまです。
言語聴覚士の仕事内容
言語・認知の訓練
普通に言語を理解し、話せていた人でも病気や事故をきっかけにある日突然、「言葉が話せない」「理解・表現ができない」などの状況に陥ることがあります。言語聴覚士はこうした患者さんに対し、「言葉を聞いて理解する」「文字を書いてみる」などのプログラムを組んでリハビリを行います。
また脳卒中や脳梗塞、脳外傷により認知機能が落ちる場合があり、高次脳機能の回復を担うのも仕事です。こうしたケースでは、見当識や注意、空間認識能力などの訓練を通じて機能改善を図ります。
発声・発語の訓練
「声がうまく出せない」「呂律が回らない」などの症状があると、コミュニケーションを取るのが難しくなり、QOL(Quality Of Life)が低下します。こうしたケースで、発声・発語の訓練を行い機能改善や回復を目指すのも、言語聴覚士の重要な仕事です。
具体的には、声練習や発声のコツを身につけるための音声リハビリテーションや、はっきりと言葉を発声するための構音練習などを行います。
摂食嚥下の訓練
人間が生きていく上で、口から食べ物を摂取して栄養を得ていくことが欠かせません。しかし、脳卒中後や加齢の他、頭頸部の手術後は嚥下機能が低下するケースがあります。その状態のままでは、栄養不足に陥ったり、誤嚥性肺炎を起こしたりする可能性があり危険です。
言語聴覚士は、患者さんが安全に食べ物を食べて嚥下し、栄養を摂取できるようにサポートします。嚥下訓練は大きく分けて、実際に食べ物を食べる直接的嚥下訓練と、嚥下に使う筋肉を鍛えたりマッサージや運動をしたりして機能改善を図る間接的嚥下訓練の2つです。
聴覚の訓練
加齢や病気・けがにより聴覚障害が後天的に生じる場合もあれば、先天的に耳が聞こえにくい場合もあります。こうした患者さんが音を聞き取り、正しく理解して、反応できるようにリハビリを行うのも、言語聴覚士の重要な役割です。
聴覚の訓練では、まず患者さんに聴覚検査や耳の聞こえにくさのヒアリングをするなどして症状を把握します。補聴器や人工内耳の適応訓練を行うケースもあります。
小児の言語・認知の訓練
言語聴覚士には、小児の言語・認知機能が向上するようにサポートし、健全な発達を促す役割もあります。
自閉スペクトラム症(ASD)や発達性言語障害(DLD)などにより、先天的に言語理解能力が低い小児がみられます。また吃音や構音障害が原因でうまく言葉が発せられないなど、症状はさまざまです。小児領域では、個々の状態に合わせてリハビリのプログラムを組むことが重要となります。
目の前の子どもとコミュニケーションを取りつつ、家族に適切なアドバイスをするのも欠かせません。
言語聴覚士の就職先や活躍の場
言語聴覚士の就職先や活躍の場には、以下のようなものがあります。
- 医療機関
- 福祉施設
- 教育機関
- 独立開業
言語聴覚士の主な就職先は、総合病院やリハビリテーション病院などの医療機関です。脳卒中・脳梗塞後の失語症、嚥下障害の患者さんを対象に、急性期から回復期、維持期にわたりリハビリを行います。
介護老人保健施設や障害者支援施設などの福祉施設で働く言語聴覚士もいます。患者さんが社会復帰できるようにリハビリを提供するのが主な役割で、訪問リハビリテーションやデイサービスなどの形態で働くことも可能です。
ろう学校や養護学校、特別支援学校、児童相談所などの教育機関で活躍する言語聴覚士もいます。児童がスムーズにコミュニケーションできるようにサポートしたり、家族からの相談に乗ったりするのが主な役割です。
資格を生かして独立開業する道もあります。リハビリは医師の指示の下で行う医療行為ですが、セミナーの開催や自費診療のリハビリ施設の開院などは言語聴覚士のみでも行えます。
言語聴覚士の一日の仕事の流れ
言語聴覚士の一日の仕事の流れを、病院勤務と福祉施設勤務の例に分けて詳しく見ていきましょう。
病院勤務の例
言語聴覚士の多くが、病院で働いています。働く病院により詳細は異なりますが、基本的にリハビリは日中に行うので、言語聴覚士は朝から夕方まで勤務するのが一般的です。
病院に勤務する言語聴覚士の一日の流れは、以下のようなイメージです。
| 時 刻 | 勤 務 内 容 |
|---|---|
| 8:30~ | 出勤。本日のスケジュールをチェックする。 勤務先によってはリハビリ業務に入る前に多職種カンファレンスが開かれることもある。 |
| 9:00~ | 午前のリハビリ開始。担当する患者さんの言語訓練を行う。 |
| 12:00~ | 患者さんの昼食時間に合わせて、嚥下機能を評価したり、嚥下訓練を行ったりする。 |
| 13:00~ | 昼休憩。 |
| 14:00~ | 午後のリハビリ開始。担当する患者さんの補聴器の適合訓練を行う。 |
17:00~ 17:30 | 本日の振り返り、明日への申し送りをして退勤。 |
福祉施設勤務の例
福祉施設(老人ホーム)に勤務する言語聴覚士の一日の流れは、以下の通りです。
| 時 刻 | 勤 務 内 容 |
|---|---|
| 8:30~ | 出勤。本日のスケジュールをチェックする。 スタッフ同士で患者さんの状態や連絡事項を共有する。 |
| 9:00~ | 午前のリハビリ開始。施設利用者とレクリエーションを通じてリハビリを行う。 |
| 12:00~ | 患者さんの昼食時間に合わせて、嚥下機能を評価したり、嚥下訓練を行ったりする。 |
| 13:00~ | 昼休憩。 |
| 14:00~ | 午後のリハビリ開始。コミュニケーションの訓練を行う。 |
17:00~ 17:30 | 本日の振り返り、明日への申し送りをして退勤。 |
一口に福祉施設といっても、老人ホームから療育施設、放課後デイサービスなど幅広い形態があります。また福祉施設では、病院などの医療機関とは異なり、レクリエーションへの参加や介護士との連携などが求められるケースがあります。勤務先によりスケジュールや勤務内容が大きく変わる点は把握しておきましょう。
言語聴覚士の魅力・やりがい
生きる上で重要な機能回復の手助けができる
「話す」「聞く」「言葉を理解する」などは生命維持には直接関わりませんが、生きていく上で重要な機能です。仮にこれらの機能が失われてしまった場合、コミュニケーションが取れずに、生きがいをなくしてしまう患者さんもいるかもしれません。また嚥下ができなければ、食べる楽しみを失ってしまうことになります。
言語聴覚士はこのような重要な機能回復の手助けができ、患者さん自身に「生きる喜び」を感じてもらうことで、大きなやりがいを得られます。
患者さんと向き合える
患者さんと真剣に向き合い、言語や認知、聴覚、嚥下機能の改善を支援できるのが、言語聴覚士の魅力です。本人や家族とコミュニケーションを取りながら病歴を聴取し、今の状況と照らし合わせて個別化したリハビリプログラムを組みます。
「発声しにくそうにしていた患者さんが、前より喋れるようになった」「嚥下訓練を積んで、食べる楽しみを見出せるようになってきた」など、患者さんの変化を直接感じられるのも大きなやりがいです。
子どもの発達に関われる
子どもの発達を直接見届けられる点も、言語聴覚士のやりがいです。
生まれつき、ことばや聞こえ、食べることに問題を抱えている小児を対象に、リハビリを行います。無事に進学できたり、学校生活で友達と楽しんだりした姿を見ると、言葉にできないような達成感を味わえます。
専門性が高い仕事である
言語聴覚士は、言語や摂食・嚥下などの機能改善を図る専門性が高い仕事です。
言語機能のリハビリでは、言語機能障害を持つ患者さんに対して、発語能力や言語理解をサポートします。例えば脳梗塞や脳の外傷により、「言葉が理解できない」「伝えたいことをうまく表現できない」「スムーズに会話できない」などの失語症を患うことがあります。
構音機能に障害はないものの、うまく喋れないまたは理解できない状態は患者さんにとって苦痛です。そこで言語聴覚士は、コミュニケーション能力を維持するために簡単な会話や挨拶をしたり、文字を書いてもらったりするなどのリハビリを行います。急性期・回復期・維持期で具体的なリハビリ方法は異なり、高い専門性が必要です。
高度な専門性を生かして患者さんをサポートできれば、やりがいも感じられるでしょう。
言語聴覚士に向いている人の特徴
言語聴覚士に向いている人の特徴は、以下の通りです。
- コミュニケーション能力が高い
- 人と関わり合うのが好き
- 粘り強さがある
まず挙げられる特徴が、コミュニケーション能力の高さです。リハビリは患者さん本人はもちろん、家族や他の医療スタッフと関わり合いながら進めていきます。そのため患者さんが何を伝えたいのか、どうして欲しいのかを読み取れる人に向いています。
人と関わり合うのが好きな人にも向いているでしょう。関わる中でささいな変化にも気付ければ、必要なリハビリプログラムを組めるでしょう。
また粘り強さも欠かせません。リハビリを行っても、必ずしもすぐに成果が現れるわけではないので、患者さんに寄り添いながら長期的にサポートしていく必要があります。
言語聴覚士になる方法
言語聴覚士になるには、高校卒業後に文部科学省または都道府県知事が指定する専門学校・短期大学・4年制大学にて専門課程を修了し、国家試験に合格すると資格を取得できます。
言語聴覚士国家試験は例年2月に実施され、以下の内容が問われます。
- 基礎医学
- 臨床医学
- 臨床歯科医学
- 音声・言語・聴覚医学
- 心理学
- 音声・言語学
- 社会福祉・教育
- 言語聴覚障害学総論
- 失語・高次脳機能障害学
- 言語発達障害学
- 発声発語・嚥下障害学および聴覚障害学
このように幅広い知識が問われるので、十分な対策が必要です。
言語聴覚士の平均年収
言語聴覚士を目指す上で気になるのが、その平均年収です。
厚生労働省が公表した「賃金構造基本統計調査」によると、2023年の言語聴覚士(理学療法士・作業療法士・視能訓練士を含む)の平均月収は30万円、年間賞与やその他の特別支給額は71.4万円です。これらを元に計算すると、平均年収は431.4万円となります。
国税庁の調査「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均給与は460万円なので、やや少ないと感じるかもしれません。しかし勤務年数や勤務地によって異なりますが、経験を積むことで年収が500〜600万円となるケースもあります。
※参考:e-Stat 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 」
※参考:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
言語聴覚士の将来性
今後の日本は、さらに少子高齢化が加速すると予想されています。高齢化が進むと、認知症後の認知機能の改善、誤嚥性肺炎の予防、聴覚の訓練が必要となるので、言語聴覚士の需要は増します。
また言語聴覚士が活躍できる場は医療機関・医療福祉・介護・教育の枠を超えて広がるとも予想されており、十分に将来性が期待されています。
まとめ
言語聴覚士は、言語や認知、発声、嚥下、聴覚に関するリハビリのスペシャリストです。医療機関や福祉施設だけでなく、教育機関で働くことや独立開業する選択肢もあります。
仙台青葉学院短期大学の言語聴覚学科では「その人らしさ」を支援・サポートできる言語聴覚士になるための専門的なカリキュラムを組んでいます。1年次から3年次にかけて専門支持科目・専門展開科目・専門独自科目、演習、実習を通じてより実践的なスキルを身につけることが可能です。早期の国家試験対策授業・オリジナルの模擬試験・オンライン学修管理システムを用いた国家試験対策など、国家試験の支援プログラムも充実しており、最短の3年間で言語聴覚士を目指せます。
言語聴覚士を目指している方は、ぜひ仙台青葉学院短期大学にお問い合わせください。