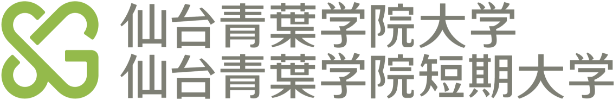公務員保育士とは?私立保育士との違い、メリット・デメリット、採用までの流れを解説
保育士の働き方には、民間企業などが運営する私立保育園で働く以外に、公立の保育園や保育施設で公務員保育士として働く方法があります。どちらも同じ保育士資格を取得して働く仕事です。しかし公務員保育士は私立の保育園で働く保育士とは、採用までの流れの他、働き方や給与、待遇など異なる点が多くあります。
本記事では、公務員保育士と私立保育園で働く保育士との違いをはじめ、給与やメリット・デメリット、採用までの流れと注意点などを解説します。
公務員保育士とは?
公務員保育士とは、地方自治体が運営する公立の保育園や保育施設などで地方公務員として働く保育士です。公務員保育士は地方公務員という立場であるため、保育士としての資格取得が求められることに加えて、地方公務員の採用試験に合格する必要があります。
地方公務員として働くため、民間の保育園勤務よりも安定した収入が期待できるのが特徴です。しかし、公務員保育士は地方公務員と同等に扱われる好条件であることから、採用試験の倍率が高まっていること、近年公立の保育施設数が減少傾向にあることから、公務員保育士として正規職員で働くのは狭き門だといわれます。
公務員保育士は正規職員としてフルタイムで働くのが基本ですが、地方自治体によっては臨時職員や非常勤職員を募集しているケースもあり、こちらは公務員採用試験の合格は問われません。
公務員保育士と私立保育士の違い
私立の保育施設で働く保育士と公務員保育士は、いずれも保育士の資格が必ず求められる仕事ですが、働き方に大きな違いがあります。
勤務場所
公務員保育士の勤務場所は、自治体が運営する公立の保育施設です。勤務場所には保育園の他、児童養護施設なども含まれます。一般的な保育士と比較すると、公務員保育士の勤務場所となる公立の保育施設は私立よりも少ない傾向があるため、その数や種類は少なめです。
当然ながら、公務員保育士の勤務場所は所属する自治体内にある施設のみとなるため、別の自治体の施設で働くことはありません。
勤務時間
私立の保育園は施設ごとに勤務時間やサービス内容に違いを設けている場合もあるので、休日保育や延長保育、夜間保育の発生などで保育標準時間が長く設定されている場合、勤務時間が長くなるケースもあります。
一方、公務員保育士の勤務時間は、地方自治体ごとに定められた勤務時間に準じます。公務員保育士が働く公立の保育園では、保育標準時間が明確に定められていること、延長保育や休日保育がほとんどないことから残業や夜間の勤務が少なく、基本的にカレンダー通りの勤務です。公務員の勤務時間に準ずるため、どの施設で働いていても毎日の勤務時間が大きく変わることはほとんどありません。
ただし、近年は保護者のニーズに合わせるために、保育時間を長くしたり土曜日に保育を行ったりする公立保育園も増えています。そのような保育園での勤務の場合、公務員保育士の勤務時間も変わってくる可能性があります。
保育方針
保育方針は、日本国内全ての保育園で統一されているものではありません。私立の保育園は施設や運営元ごとに異なる保育方針で運営されているため、転職などで別の運営法人の保育園で働いた場合、保育方針が異なることで前職と全く異なる保育が求められることがあります。
公立の保育施設は、自治体ごとに同じ保育方針の元で運営されています。そのため、同じ自治体内で別の保育施設へ異動した場合でも、前職と同じ保育方針の元で勤務可能です。
異動の有無
私立の保育園は基本的に異動がないケースが多く、たとえ異動があったとしても同じ運営元の保育園や保育施設で、勤務環境が大きく変わることは比較的少なめです。
これに対し、公務員保育士は所属する地方自治体が運営する保育施設間で定期的に異動が発生します。一般的に2~4年に一度のペースで異動が行われるので、同じ施設で4年以上働くことは難しいといえるでしょう。異動先の希望が通るとは限らず、保育園で働くことを希望していたとしても、保育園以外の施設へ異動となるケースもあり得ます。
採用条件
私立の保育施設では、施設や運営元ごとに採用条件を定めており、採用方法も異なります。
公務員保育士は、保育士資格を取得した上で公務員採用試験に合格するのが採用の必須条件です。さらに、自治体によっては居住していることや幼稚園教諭免許の有無、保育士としての経験などが採用条件に含まれている場合もある点が、私立の保育施設での保育士採用とは大きく異なります。
公務員保育士の給与
厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」によると、2023年度の保育士の平均給与月額は27万1400円でした(※1)。総務省が公表している令和5年の「地方公務員給与実態調査」によると、公務員保育士の平均基本給月額は30万7482円であるため、公務員保育士の平均給与の方が約3万円以上高いことが分かります(※2)。
公務員は毎年昇給があり、勤続年数が長くなるほど給与が上がるため、同じ勤続年数でも勤務期間が長い場合は私立保育園で働く保育士と給与の差が大きくなる傾向があるのが、公務員保育士の給与の特徴です。
※1参考:政府統計の総合窓口 e-Stat「令和5年度賃金構造基本統計調査」
※2参考:総務省「令和5年地方公務員給与実態調査結果の状況」
公務員保育士のメリット・デメリット
公務員保育士は私立保育園で働く一般的な保育士とは異なる勤務となることで、メリットやデメリットが発生することがあります。具体的に公務員保育士にはどのようなメリットやデメリットがあるのか、それぞれ解説していきます。
メリット
公務員保育士の大きなメリットの一つは、安定した給与です。前述の通り、地方公務員と同様に毎年昇給するので、勤続年数が長ければ長いほど給与アップが期待でき、さらに賞与も支給されます。また公務員保育士は、地方公務員として充実した福利厚生を受けられる点もメリットです。
加えて前述の通り公務員保育士は勤務時間が明確に定められており、一定のリズムを保って勤務ができます。公務員であるため失業のリスクも少なく、突然仕事を失う心配がほぼない点も公務員保育士のメリットの一つです。
私立の保育園では、転職などで勤務先が変わると、異なる保育方針の元で働く必要が出てきます。一方、公務員保育士の場合は保育方針が統一されている公立の保育施設で働くので、勤務場所に関わらず同じ保育方針なので働きやすい点もメリットです。
そして、公務員保育士は地方公務員として身分が保障される点も大きなメリットでしょう。社会的信用が高いため、住宅ローンやクレジットカードの申し込みなどの審査に比較的通りやすくなります。
デメリット
公務員保育士のデメリットは、採用までのハードルがやや高いことです。公務員保育士として働くには、保育士資格を取得した上で公務員採用試験に合格する必要があり、まずはしっかりと対策をして合格を目指す必要があります。公務員保育士を希望する人が多い中、採用枠が限られているため競争率は高めですが、その分合格した際の達成感や安定した働き方が期待できます。
公務員保育士ならではの特徴として、数年ごとに異動が発生することがあります。これにより、同じ施設で長期間働くことは難しいかもしれませんが、異動を通じて新たな環境や保育施設での経験を積むことができます。異動先が希望通りにならない場合もありますが、多様な経験を得られる機会と捉えることで、保育士としてのスキルをさらに広げることが可能です。
また、公務員は法律上、副業が制限されているため、公務員保育士も原則として副業は行えません。この点は、自由な働き方を求める方にとっては制約と感じられる場合もありますが、その一方で、公務員保育士としての本業に集中しやすい環境といえます。安定した収入や待遇が確保されているため、他の仕事に頼る必要が少ないのも公務員保育士の特徴といえるでしょう。
公務員保育士になるには
公務員保育士になるには、まず保育士資格を取得するのが大前提です。公務員保育士を目指すための公務員採用試験は、保育士の資格を取得、または取得見込みであれば受験できます。
公務員採用試験は原則的に年1回、6~9月頃に実施されますが、自治体によっては、1~2月、3~4月頃に試験を実施する場合もあります。各自治体によって受験資格や試験日程などが異なるため、受験する自治体の情報収集が必須です。
一般的な公務員採用試験は、出願後に一次試験として筆記試験、二次試験で面接や実技試験、小論文などを行いますが、採用人数が多い場合は三次試験で面接や実技を実施することもあります。
公務員採用試験合格者は採用候補者名簿に1年間登載され、その間に保育施設から採用通知を待つのが、公務員保育士になるための流れです。採用候補者名簿に載ってすぐに保育士としての仕事が決まるわけではないため、1年間の登載期間中に採用通知が来なければ、勤務先が決まらない可能性もあります。
公務員保育士採用試験の選考日程・内容
前述したように、公務員保育士になるために必要な公務員採用試験の詳細は自治体によって異なります。東京都新宿区での選考日程や選考内容を例にすると、2024年度は35名程度の採用予定数で、主な勤務先は保育園の他こども園や子ども総合センター、児童館などです(※)。
公務員保育士採用試験の受験資格は、採用時点で20歳以上38歳未満という年齢制限が設けられています。保育士資格を取得または2025年3月31日まで取得・登録見込みで都道府県知事の登録を受けている、または幼稚園教諭免許所有者で保育士資格と都道府県知事の登録を受けていることも、受験資格を得るための条件です。
インターネットの申し込みフォームで受験を申し込むと、受験票と履歴書がメールで送付されます。これらを印刷し、履歴書に写真を貼付した2種類の書類を試験当日に持参して受験となります。
試験は8月の一次選考、10月の二次選考の2回です。一次選考では20問の五肢択一問題が一般教養分野と保育に関わる専門分野で出題され、1000字程度の課題式作文を60分で作成します。一次選考を通過した者が、二次選考の個別面接へ進み、合格者が新宿区職員として採用となります。
※参考:新宿区「令和6年度新宿区職員募集案内(福祉)」
公務員保育士に向いている人、向いていない人
公務員保育士に向いているのは、できるだけ長く働きたい人です。結婚や出産後などライフステージが変わった後も働きやすく、勤続年数が長くなるほど給与が上がる点もメリットとなるでしょう。異動が多い仕事であるため、異動が苦にならない人や他地域へ引っ越す予定がない人、保育園以外のさまざまな施設で働きたい人にも公務員保育士の仕事が向いています。
公務員保育士に向いていないのは、同じ施設で働き続けたい人です。公務員保育士は定期的に異動が発生する仕事なので、職場が変わることに抵抗がある人には向いていません。また公務員保育士は保育園以外で働く機会もある仕事です。保育園のみでの勤務を希望している人にも、向いていないといえるでしょう。
公務員保育士を目指すときの注意点
公務員保育士を目指す際に注意したいのが、公務員採用試験に合格したとしても、必ず公務員保育士として働けるわけではない点です。採用候補者名簿に登載されている間に採用が決まらなかったけれど引き続き公務員保育士としての勤務を希望する場合は、再び公務員採用試験を受験しなければなりません。
公務員保育士は、常に募集があるわけではない点に注意が必要です。基本的に欠員が出た場合に募集されるため、勤務先を選ぶことが難しいケースもあります。保育園以外の施設に配属されることもあり、保育園で勤務していたとしても他の施設へ異動となることも考えられ、希望通りの勤務先や勤務場所の選択は原則的に難しいといえるでしょう。
まとめ
公務員保育士になるには、公務員採用試験に合格してから採用通知を待つ必要がありますが、言うまでもなく保育士資格取得は必須です。公務員保育士を目指す方で保育士資格を取得していない方は、まずは保育士資格を取得しましょう。
仙台青葉学院短期大学では、保育士資格取得を目指せるこども学科を設置しています。少人数制のゼミや実践的な実技指導などを通して基礎的な知識や技能をしっかりと身に付けられ、保育士や幼稚園教諭二種免許、社会福祉主事任用資格などの取得が可能です。公務員を目指す学生を対象とした公務員試験対策講座も実施しており、公務員保育士を目指すのに適した環境です。公務員保育士を目指すなら、仙台青葉学院短期大学こども学科で知識や技術、保育士資格を取得してみてはいかがでしょうか。