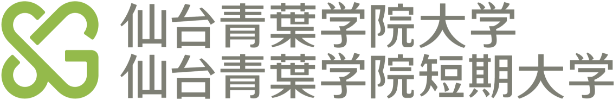大学編入とは?受験条件や時期、難易度、メリット、成功のポイントを解説
大学は一般入試に合格して入学する方法以外に、短期大学や専門学校などから途中年次へ入学する「編入」という方法もあります。大学に編入するには編入学試験の受験が必要で、一般入試とは異なる科目や実施方法であるため編入学試験向けの対策が必要です。そこで本記事では、大学編入の基本やメリット・デメリット、大学編入を成功させるためのポイントなどを解説します。
大学編入とは
大学編入とは、正式には「編入学」と呼ばれており、文部科学省では「学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)」と定義しています。
文部科学省では「学校を卒業した者」を対象としていますが、大学編入は現在専門学校や短大、大学に在学中の学生が別の大学へ入学することも含まれます。
※参考:文部科学省「大学への編入学について」
大学編入の学年と受験条件
大学に編入する際の学年は、3年次からの編入が一般的です。3年次からの編入を実施している大学が多いためで、一部の大学では2年次や4年次で編入できるところもあります。
大学編入の条件は、短期大学または高等専門学校の卒業者、4年制大学の2年次修了者、専門学校において修業年限2年以上、総授業数1700時間または62単位以上の専門課程を修了した者のいずれかです。加えて、編入先となる大学ごとに条件が設定されていますが、一般的には2年次編入で30単位以上、3年次編入で60単位以上の取得見込みであることも求められます。
大学編入学試験の時期
大学編入学試験の時期は受験対策に関わるので、必ず押さえておきましょう。大学編入学試験の時期は理系と文系で異なり、学部ごとにスケジュールが公表されるため、志望する学部のスケジュールを確認してください。
一般的な大学編入学試験の試験日は、文系が8~12月、理系が5~8月です。それぞれ募集要項の公表日は試験日のおよそ3カ月前となるので、文系が6~8月、理系が3~5月です。編入学試験は、例年実施していたとしても募集が停止されることがあるので、志望大学の公表時期が来たら募集要項を小まめにチェックすると良いでしょう。
大学編入学試験の志願者傾向・難易度
文部科学省が公表した2024年度の学校基本調査 によると、大学への編入学者数は6228名、うち短期大学からの編入学者数の割合が最も多く、3039名と5割弱を占めていました(※)。このことから、大学編入学試験の志願者は短期大学からの編入学が多い傾向があるといえるでしょう。
大学編入学試験の難易度は、一般的な入学試験よりも高めです。まず、大学の編入学は募集数が定められています。その数は若干名、多い場合でも10名程度なので、決して多くはありません。編入学試験では編入する年次と同等の学力が必要であるため、一般の入学試験よりも専門的な知識が求められ、難易度が高くなります。
編入学試験は専門性を求められるため、一般の大学入学試験よりも科目数が少なく、論述式の専門科目と英語、面接のみというケースが多いのが特徴です。
※参考:政府統計の総合窓口「学校基本調査 令和6年度 高等教育機関 学校調査 学校調査票(大学・大学院)」
大学編入にかかる費用
大学編入にかかる費用は、編入学試験の受験料として国公立大学で約3万~3万5000円が目安です。私立大学の場合は、大学によって受験料が異なります。
出願時には出身学校での卒業証明書や卒業見込証明書、単位取得証明書などの作成費用に実費がかかります。遠方の大学を受験する場合は、交通費や宿泊費などがかかることもあるでしょう。そして、編入学試験に合格して入学するときには入学金と学費の支払いが必要です。国公立大学と私立大学の違い、学部によって費用は大きく変動します。
塾や予備校で受けられる大学編入対策は、編入学試験合格を目指す際に有効な手段ですが、受講するには30~70万円程度かかります。
大学への編入学では入学金がかかることと、編入対策を受ける場合の費用を考えると、1年次から入学するよりもかかる費用が増えると考えて良いでしょう。
大学編入学のメリット
大学編入には、一般入学とは異なる以下に挙げるメリットが期待できます。
諦めていた大学に挑戦できる
一般入試で第一希望だった大学に合格できず入学を諦めたり、試験日程が他の大学と重複して受験できなかったりしたケースはあるでしょう。また専門学校や短期大学に入学してからも志望大学を諦めきれなかった方でも、編入学であれば志望大学に挑戦できるのが大きなメリットです。
2年次で編入できる大学であれば、2年次の編入学試験で不合格だったとしても、3年次に再度挑戦できるチャンスがあるのも、編入学のメリットといえるでしょう。
興味のある分野の学びを深められる
短期大学や専門学校などで学んでいるうちに、興味のある分野についてもっと深く学びたい思ったとき、大学へ編入学することによって、より深く学べるメリットがあります。
また学んでいるうちに、現在の専門分野とは別の分野について興味を持ったり、その分野が自分に向いていないと思ったりすることもあるでしょう。すでに学んでいる短期大学や専門学校での専門分野の変更は難しいことがありますが、大学へ編入学することで、自分に合った分野を専攻して学べます。
学歴を高めて可能性を広げられる
将来希望する就職先の採用条件に「大学卒」があると、短期大学卒や専門学校卒では応募できません。しかし、大学へ編入して卒業できれば「大学卒」の学歴を得られ、就職先の幅も広がることが期待できるメリットがあります。
学歴は、その後の人生に大きな影響を与える場合があります。学歴を高めることが自信につながり、就職後の人事や昇給にも良い影響を与えられる他、自分自身の可能性が広がる機会にもなるでしょう。
卒業までのタイムロスが少ない
大学に編入学した場合は、現役の学生と同じく4年次で卒業となります。一般試験で1年次から大学に入学し直したり、浪人したりするよりも卒業までのタイムロスが少なく済む点は、編入学のメリットの一つです。
大学受験よりも併願しやすい
一般の大学受験では国公立大学の二次試験日程が重複することが多いため、基本的に前期・後期それぞれで1校のみしか受験できず、併願はほぼ不可能です。
一方、編入学試験は国公立大学でも試験日程は大学ごとに異なるので、編入学試験の日程が重複していなければ大学受験よりも併願しやすいメリットがあります。
試験科目が少ない
前述した通り、編入学試験の試験科目は一般入試より少なめです。特に国公立大学での一般入試では大学入学共通テストの5教科7科目の受験が必須なので、幅広い科目の受験対策が求められます。
編入学試験は、国公立大学であっても専門科目の小論文と英語、面接の3種類のみが一般的です。一般入試と比較すると試験科目が少なく、大学入学共通テストを受験する必要もないので試験対策を集中的に行いやすいのも、大学編入のメリットといえます。
大学編入のデメリット
大学編入には多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットもあります。
まず、通学しながら受験準備・対策をしなければならない点です。編入学試験は一般入試よりも科目数が少ないので負担も軽減できると思われがちですが、短期大学や専門学校などに通いながら行うことが負担となる場合があります。
また大学への編入は、周囲の学生が1年次から人間関係を築いている状況に飛び込むこととなるため、新しい環境へ適応しなければなりません。
加えて編入学試験に合格していたとしても、いざ授業を受けてみると難易度が高く、ついていけなくなる可能性があります。その上、編入学後の単位互換数が少ないと、単位取得の負担が大きくなる状況もあり得るでしょう。
そして、大学編入は一般的に3年次からの入学となりますが、この時期は就職活動をスタートする時期でもあります。新しい環境で学ぶと同時に就職活動も考慮する必要があり、想像以上に負担が大きくなることも、大学編入のデメリットです。
大学編入後の就職は不利になる?
大学編入は進路を変更することになることがあるため、将来的に就職に不利になってしまうのではないかと不安に感じるかもしれません。前述したデメリットからも、就職活動を開始する時期に編入すること、新しい環境に慣れず授業についていけず単位を落としてしまう可能性があることも、大学への編入が就職に不利になると思われがちな理由です。
しかし、大学に編入したことが就職に不利に働くことはないといえます。同学年の学生が就職活動を開始する時期に新たな環境で学ぶことは、就職活動に割く時間が減る点で負担が増えることは確かですが、就職活動と学習の両立は自分自身でスケジュールの調整が可能です。むしろ大学編入は、向学心をアピールできるため、就職に有利になることが期待できます。
大学編入を成功させるポイント
大学編入は一般入試とは異なる点が多く、試験対策の方法も異なります。大学編入を成功させるためには、編入学時に必要な条件をクリアすることが第一のポイントです。そこで、以下でご紹介する5つのポイントを押さえておきましょう。
在学中の成績を上げる
大学編入には、成績証明書の提出が求められる場合があります。一般入試よりも受験科目数が少ないため、在学中の成績が重要視されるからです。編入学試験の成績が良かったとしても、在学中の成績によっては不合格になってしまうかもしれません。そのため大学編入を目指す方は在学中の短期大学や専門学校で成績を上げておくことが、編入を成功させるためのポイントとなります。
英語力を高める
編入学試験では英語が含まれることが一般的で、TOEICやTOEFLなどの英語検定試験の成績提出が必要な場合があります。編入学試験はまず英語の試験で一定の点数を獲得することが求められ、その上で残りの科目や小論文、面接の成績を加えて総合的に判断される形であるため、英語の成績を上げることは編入を成功させる上で重要となります。
大学への編入を見据えている方は、まず英語力を高めておくのがおすすめです。
情報収集や過去問対策をする
一般入試にもいえることですが、試験問題は大学ごとに内容が異なるので、編入学試験においても過去問対策は必須です。過去問から、出題傾向を把握しておきましょう。
編入学試験では、志望する学部の専門科目が題材の小論文が課される場合があります。時事問題が取り上げられる場合もあるため、日頃からニュースなどの最新情報をチェックしておくことも、試験対策となります。
志望理由書を丁寧に書く
大学の編入学出願の際は、志望理由書を提出します。志望理由書は、一般入試でも面接がある大学で提出が必要な書類で、編入学試験ではほとんどの場合において作成が必要です。
編入学試験での面接は、志望理由書の内容を元に行われます。この大学で学びたい理由、学習計画や卒業後のビジョンなどを盛り込みましょう。何を学んでどう生かしたいのかを、丁寧に読みやすく書くことが、大学編入成功のポイントです。
予備校を活用する
編入学試験対策として、予備校を活用する方法があります。予備校では、一般入試に限らず編入学試験対策を行っているところがあり、最近の動向についての情報を得られます。
編入学試験で不可欠な小論文も、予備校で添削指導を受けられるので、十分に試験対策を行いたい方は、予備校を活用することも検討しましょう。
まとめ
大学への編入は、短期大学や専門学校などで学んでいる方がさらに知識を深めたい、興味や関心を持った分野についてもっと学びたいときの選択肢の一つです。大学の一般入試とは異なる点が多い編入学試験ですが、ポイントを押さえていれば効率的に試験対策ができ、大学へ入り直したり浪人したりするよりも時間やコストを削減して学べるでしょう。
大学への編入は就職でも不利になることがないものではないため、ビジネス系の短期大学からより良い就職先を目指す方にとっても有効な方法です。仙台青葉学院短期大学のビジネスキャリア学科でも、編入学の実績豊富な教員や学生総合支援センターのスタッフが手厚いサポートを行っています。まずは短期大学でビジネスを学んだ後、そのまま就職するのではなく大学に編入することで、就職先の選択肢を広げたいと考えている方におすすめです。
短期大学から大学への編入、就職を見据えた編入を目指す方は、今回解説した内容を参考に、大学編入対策を行ってみましょう。