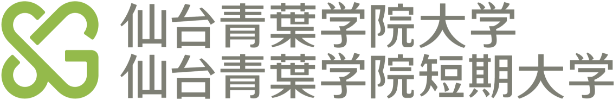「栄養士」と「管理栄養士」どっちが良い? 資格や仕事の違いをまとめて解説!
栄養士と管理栄養士はいずれも、食と栄養に関わる仕事です。どちらにも「栄養士」という言葉が含まれているので、同じ資格だと思っている人もいるでしょう。確かに共通点もありますが、違う資格です。
そこで本記事では、混同されがちな栄養士と管理栄養士の共通点と違いを、仕事内容や就職先などの観点から徹底解説します。栄養士と管理栄養士への理解を深めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
栄養士と管理栄養士の共通点
栄養士と管理栄養士の共通点はいずれも、食と栄養に関する幅広い知識を持つ点が共通しています。食事を通じて、患者さんや利用者が健康的な食生活を送れるようにサポートをするのが主な役割です。
健康増進や生活習慣病の予防を目的とした栄養指導や栄養管理、食事の提案、献立の作成なども行います。病院や学校、福祉施設、介護施設、食品メーカーなど活躍できる場が広いところも共通点です。
また食に関する正しい知識を学んでもらうための、食育の推進にも関わります。
上記の共通点に加えて、細かい条件は異なりますが、いずれの資格も、厚生労働大臣が指定する養成施設で専門課程を修了する必要があります。
栄養士と管理栄養士の違い
栄養士と管理栄養士には共通点もありますが、違う点も多くあります。栄養士または管理栄養士を目指す方はそれらを把握しておくことが重要です。
栄養士と管理栄養士の違いを、以下の観点から解説します。
資格の違い
栄養士と管理栄養士は資格の取得方法が異なります。それぞれの資格はどのようなプロセスを経て取得できるのかを詳しく見ていきましょう。
栄養士の資格
高校卒業後に厚生労働大臣が指定する栄養士養成施設に進学した後、2年以上の専門課程を修了すると、栄養士の資格を取得できます。2〜3年制の専門学校・短期大学、4年制の大学で栄養士の専門課程を学ぶことが可能です。詳しくは後述しますが、専門課程の教育を何年間学ぶかによって、管理栄養士国家試験の受験資格が異なります。
栄養士養成施設では、以下の内容について学びます。
●生理学・解剖学・生化学
●公衆衛生学・医学概論
●食品学
●栄養学
●調理学
●食品加工学
●食品衛生学
●食品とアレルギー
●子どもと食育
現場に出て活躍するためには、座学に加えて演習や実習が充実している学校を選ぶのが良いでしょう。
管理栄養士の資格
指定の教育課程を修了すると得られる栄養士と異なり、管理栄養士は管理栄養士国家試験に合格すると取得できます。国家試験を受験するには、以下の条件を満たさなければなりません。
●2年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士の資格を得た者:3年以上の実務経験を経ること
●3年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士の資格を得た者:2年以上の実務経験を経ること
●4年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士の資格を得た者:1年以上の実務経験を経ること
●4年制の管理栄養士養成施設を卒業して規定の期間までに栄養士の免許を受けること
また管理栄養士国家試験では、以下の内容が問われます。
●社会・環境と健康
●人体の構造と機能および疾病の成り立ち
●食べ物と健康
●基礎栄養学
●応用栄養学
●栄養教育論
●臨床栄養学
●公衆栄養学
●給食経営管理論
上記が幅広く問われる試験において、およそ60%の点数が合格基準です。
※参考:厚生労働省.「管理栄養士国家試験」.
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/ ,(参照 2024-01-15).
業務を行う対象の違い
業務を行う対象も若干の違いが見られるので、栄養士と管理栄養士のそれぞれの場合を詳しく見ていきましょう。
栄養士が業務を行う対象
栄養士が業務を行う対象となるのは、主に健康な人です。年齢層は幅広く、乳幼児から成人、高齢者までを対象としています。
栄養士は学校や保育園、学生寮・社員食堂などで、集団を対象に食事管理・提供を行います。具体的には栄養バランスの取れた食事を提供し、学生が成長期に必要な栄養を取れるように、社員が生活習慣病を予防できるようにサポートするのが役割です。
健康な人を対象とするので、食品メーカーや飲食店で働き商品開発に携わることもできます。
一方で、病気の治療や高齢者特有の栄養課題に対して積極的なアプローチをするのは、栄養士の業務範囲外となるケースもあります。
管理栄養士が業務を行う対象
管理栄養士が業務を行う対象には、先述した栄養士の業務対象に加えて、病気を患っている人や健康課題を抱えている人も含まれます。主に病院や介護施設などの現場で、患者さんの健康状態や治療の進行具合に合わせて食事を管理するなど、栄養士よりも高度な専門知識が必要で対応範囲が広いのが特徴です。
また健康増進法第21条により、特定給食施設には、管理栄養士の配置が義務付けられています。特定給食施設とは、特定かつ多数の人を対象に継続的に食事を提供する施設で栄養管理を必要とする施設です。こうした施設では、より高度で専門的な食と栄養の知識、栄養指導、給食管理の知識が必要となるので、管理栄養士のみが業務を行えます。
※参考:e-GOV 法令検索.「健康増進法」.
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103#Mp-Ch_5-At_21 ,(参照 2025-01-14).
仕事内容の違い
食と栄養に関わる点では共通していますが、細かい仕事内容を見ていくと違いが見られます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
栄養士の仕事内容
栄養士の仕事内容は、主に以下の通りです。
●栄養指導・栄養管理
●食事の管理・提供
●食育の推進
栄養指導や栄養管理とは、個人または集団に対して生活習慣やライフスタイルに合わせた食事方法を指導・管理することです。例えば、アレルギーの有無に合わせて食事内容を変更したり、生活習慣病の予防のために指導したりするなどです。
給食センターや食堂で働く栄養士は、食事の管理・提供を行います。ただ単に食事を提供するだけでなく、季節のイベントを取り入れて食事を楽しめる雰囲気を演出する工夫も求められます。
食育とは、食に関する正しい知識を広げる教育活動です。食育基本法が制定されており、国民が生涯にわたって健康的に生活できるように国や自治体が取り組むべきことや責務が定められています。栄養士は学校や職場、地域で幅広い年齢層を対象に食育を推進します。
管理栄養士の仕事内容
管理栄養士は上記の栄養士の仕事に加えて、以下の業務も担います。
●健康に課題がある人への栄養指導・食事管理
●特定用途食品の提供
●特定保健指導
管理栄養士は、健康上の課題を抱える人に対して栄養指導・食事管理を行います。業務の対象者が傷病者にまで拡大している点が、栄養士との大きな違いです。
特別用途食品とは、健康上の問題があり特別な配慮が必要となる人を対象に設計された食品です。低タンパク食やアレルゲン除去食などの病者用食品、嚥下機能が低下した用の食品などが該当します。特定用途食品の提供に関しても、管理栄養士が担います。
特定保健指導とは、特定健康診査の結果メタボリックシンドロームや生活習慣病に該当する群、またはそのリスク群に対して、食生活や栄養に関する指導をすることです。正しい知識を伝え、行動するモチベーションを高めるコミュニケーション能力が求められます。
就職先の違い
ここでは、栄養士と管理栄養士の就職先の違いを解説します。
栄養士の就職先
栄養士の主な就職先は、病院や福祉施設、介護施設などです。患者さんや利用者に対して消化しやすい流動食や、栄養素を調整した食事を提供します。しかし、病気の症状や患者さんの状態に合わせた食事を提供するのは、管理栄養士の役割です。
学校や保育園などでも栄養士は活躍します。成長期をサポートし、子どもたちの成長を見届けられるのが魅力です。
その他、食に関する幅広い知識を生かして食品メーカーや飲食店で働く栄養士もいます。より多くの人に食を届けられるのが、大きなやりがいでしょう。
管理栄養士の就職先
管理栄養士は栄養士と同じように、病院や福祉施設、介護施設、学校、保育園、食品メーカーなどで活躍しています。病院や介護施設で働く際は、患者さんや利用者の健康状況に合わせて、医師や看護師などの他の医療従事者とチームを組んで治療に当たります。
また保健所・保健センターや研究機関、スポーツ領域など幅広い領域で活躍できるのも管理栄養士の特徴です。高度な専門知識を生かして、セミナー講師やフードコーディネーターとしてフリーランスで活動する人もいます。
給与相場の違い
栄養士と管理栄養士は、業務内容や資格取得の難易度が異なります。これは給与相場にも反映されているので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
栄養士の給与相場
厚生労働省が公表した「賃金構造基本統計調査」によると、2023年の栄養士の平均月収(企業規模計10人以上)は26.8万円、年間賞与やその他の特別支給額は68.4万円です。これらを元に計算すると、平均年収は390万円となります。(年収は平均月収を12倍し、年間賞与とその他の特別支給額を合算して計算)
勤務先で実績や経験を積んだり、新たな資格を取得したりすると、給与アップが期待できるでしょう。
管理栄養士の給与相場
厚生労働省の賃金構造基本統計調査の「栄養士」の項目には、管理栄養士も含まれており、正確な給与差に関するデータは公開されていません。
しかし一般的には、管理栄養士は栄養士の上位に位置付けられる資格であるため、給与相場も高い傾向にあります。同じ職場でも、30〜100万円の違いがあるでしょう。
どのような人が向いている?
どのような人が向いているのか、栄養士と管理栄養士に分けて見ていきましょう。
栄養士に向いている人
栄養士は、以下のような人が向いています。
●食や栄養に関して興味がある
●料理をするのが好き
●人とコミュニケーションを取ることが好き
●創意工夫が好き
●責任感やリーダーシップがある
どれか一つでも当てはまっているなら、栄養士に向いているでしょう。
管理栄養士に向いている人
管理栄養士には、栄養士よりもさらに高度な知識が求められます。そのため、継続的に新しい知識をインプットしていかなければならないため、常に学び続ける意欲が必要です。
また、患者さんや利用者の状況を踏まえながら食事プランを考える必要があります。そのため、食の知識を活かして臨機応変に対応できる力が求められます。
その他、高いコミュニケーション能力を持っている人も、管理栄養士としての素養があります。
資格取得や仕事のメリット・デメリットは?
資格取得や仕事のメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
栄養士になるメリット・デメリット
栄養士になるメリットには、以下が挙げられます。
●安定して働ける
●食と栄養のスペシャリストになれる
●日常生活で知識を活用できる
●将来性がある
栄養士は、食と栄養のスペシャリストとして、学校や病院など、さまざまな場所で活躍できます。日常生活でも知識を活用できる点もメリットです。
また健康意識の高まりや高齢化の加速、食育の推進などにより栄養士の将来性は高いと予想されている点も、メリットに挙げられます。
一方で資格を取得するには、指定の専門課程を修了する必要があり、一定の期間がかかる点は把握しておきましょう。一定の学費もかかるので、経済的な負担を削減するために日本学生支援機構(JASSO)の奨学金や自治体・学校独自の奨学金、入学金や学費が免除される制度、教育ローンなどを活用するのがおすすめです。
管理栄養士になるメリット・デメリット
管理栄養士になるメリットは、栄養士よりも幅広い領域で働ける点です。医療機関や介護施設、学校、企業、食品メーカー、スポーツ、フリーランスなどで活躍できます。医療機関においては、病気やけがの人を対象に食事メニューを考え治療に貢献でき、働きがいを感じられるでしょう。
栄養士と同様、将来性にも期待できる点もメリットです。
一方で管理栄養士の資格を取得するには、栄養士よりもさらに時間がかかります。管理栄養士養成課程を修了するか、栄養士養成課程を修了した後に一定の実務経験が必要となります。国家試験は決して簡単な試験ではないので、相応の努力も求められるでしょう。
まとめ
栄養士と管理栄養士は、食と栄養に関わるスペシャリストである点は共通していますが、資格の取得方法や業務の対象、仕事内容などの点で異なります。いずれを目指す場合でも、それぞれの違いを明確にしておくことが重要です。
仙台青葉学院短期大学の栄養学科では、2年間で栄養学のスペシャリストを目指せます。個々のライフステージやニーズに応じて豊かな食生活をサポートするための知識と技術、責任、自覚を幅広く学ぶことが可能です。
キャリアアップで管理栄養士を目指す方向けの管理栄養士国家試験対策講座もあり、卒業後でも講義を受講できます。
栄養や食を通じて人々の健康をサポートしたいとお考えの方は、ぜひ仙台青葉学院短期大学にお問い合わせください。