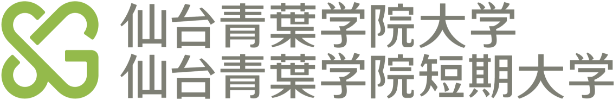栄養士とは? 仕事内容や就職先、一日の流れ、仕事の魅力・やりがいを紹介
人間が生きていく上で、食べることは欠かせません。食事の内容は体に大きな影響を与えるため、栄養バランスを考えて摂取する必要があります。しかし栄養バランスを考えた献立を作るには、一定の知識が必要です。
そこで活躍するのが、食のスペシャリストである栄養士です。病院や介護施設、学校、食品メーカーなど、幅広い場所で活躍しています。
そこで本記事では、栄養士とは何かや管理栄養士との違い、仕事内容などを解説します。記事後半では、栄養士の一日の流れや魅力、将来性などをお伝えするので、栄養士になりたいと考えている方はぜひ参考にしてください。
栄養士とは
人間が健康に生きていく上では、栄養バランスの取れた食事を摂取する必要があります。
栄養士とは栄養学に基づき、食事や栄養に関する指導や管理を行う、厚生労働大臣からの免許を受けた資格です。厚生労働大臣が指定・認定した栄養士養成施設(専門学校・短期大学・4年制大学)にて一定期間学ぶと、栄養士の資格を取得できます。
栄養士は、栄養に関するプロフェッショナルとして、多くの人々の状況やライフステージに合わせた、健康で豊かな生活をサポートします。主な仕事内容は、栄養指導・食事の管理・食育の推進などです。
栄養士は、病院、学校、福祉施設、食品メーカー、飲食店など、様々な場所で活躍しています。
栄養士と管理栄養士の違い
栄養士と管理栄養士はどの点が異なるのかが分からない方もいるでしょう。
そもそも管理栄養士は栄養士と異なり、国家試験に合格すると得られる国家資格です。栄養士免許取得後に一定の実務経験を積むか、4年制大学で管理栄養士養成課程を修了すれば、受験資格を得られます。
また業務範囲と専門性にも違いが見られます。栄養士は、健康な人を対象に、栄養バランスの取れた献立を立てたり、食材を管理したりするなど、健康な食生活をサポートします。一方、管理栄養士は、病気や健康上の問題を抱える人に対して、専門的な栄養指導や食餌療法を提供します。
栄養士の仕事内容
栄養指導・栄養管理
栄養指導とは個人または集団に対して、栄養バランスの整った食生活や栄養に関する正しい知識を指導することです。個々の年齢や生活習慣、アレルギーの有無に合わせた食事内容の提案や、食材の選定方法、具体的な調理方法までをカバーします。
栄養管理とは、栄養バランスが取れた食事を摂取できるように管理することです。健康の向上、生活習慣病の予防のために献立を考えたり、栄養状態を評価したりします。
食事の管理・提供
食事の管理・提供も、栄養士の重要な仕事です。学校、幼稚園・保育園、福祉施設などで献立を考案し、調理師と協力して食事を提供します。
献立は食べる人の年齢層や状況を考慮することが重要です。例えば、乳幼児が対象なら歯ぐきで潰せる程度の柔らかいもの、育ち盛りの小学生なら栄養バランスが取れ、かつ必要なエネルギー量を満たす食事を提供します。
味や栄養バランスはもちろん重要ですが、季節やイベントに合わせた献立を立て、食事をより楽しめる雰囲気を作る工夫も求められます。
食育の推進
食育とは、食に関する正しい知識と経験を通して、健康的で規則正しい食生活を実現できるようにするための教育活動です。日本では食育を推進するために食育基本法が制定され、国民が生涯にわたって健康的に生活できるように国や自治体が取り組むべき責務などが定められています。
食育は学校や地域、職場、家庭などさまざまな場面で実施されています。「教育」と聞くと子どもを対象に行うイメージがありますが、食育は子どもに限らず、幅広い年齢層に実施する点が特徴です。
栄養士の就職先や活躍の場
栄養士の就職先や活躍の場は、主に以下の通りです。
それぞれの場所でどのように活躍しているのかを詳しく見ていきましょう。
学校・保育園
小学校・中学校や保育園などの教育施設で働く栄養士もいます。こうした施設では主に、献立の作成や食材の発注、調理、栄養指導、食育などの業務を担います。イベントやトレンドを取り入れた食事を提供すると、食の楽しみや喜びを子どもたちに届けられるでしょう。 なお学校で働く栄養士は、学校栄養職員と栄養教諭の2つです。後者の場合、栄養士の資格に加えて、栄養教諭の免許証も必要となります。
介護施設・福祉施設
老人ホームや介護療養型医療施設では、利用者の健康維持や生活の質(QOL:Quality Of Life)の改善を食でサポートします。 具体的には、高齢者や障害者の身体状況や嚥下機能に応じて食事形態を調整したり、献立を立てたりします。 こうした施設では、ひな祭りや七夕など行事食を取り入れて食を楽しんでもらうことも重要です。
病院
栄養士は病院において、患者さんの機能回復や健康的な生活を支援するため、栄養管理や食事の提供を行います。 病態や状態に合わせて、必要な栄養量や食事形態を調整するなど、高い専門性が求められます。 医者や看護師、作業療法士などとコミュニケーションを取りながら、チーム医療で患者さんに貢献できる点がやりがいです。
食品メーカー
食品メーカーで働く栄養士の仕事は、少し特殊です。食品メーカーでは原材料からさまざまな食品を消費者に販売しますが、安心・安全でおいしい食品を作るために栄養士が活躍します。 主な仕事内容は、以下の通りです。
●商品開発:コンセプト設計を元に、試作・試食を繰り返して販売する
●品質管理:安心・安全な食品を届けるために品質を管理する
●顧客対応:顧客から寄せられた質問に対し、専門的な知識のある栄養士が回答する
飲食店
栄養士は食に関する幅広い知識を生かして、飲食店で働くことも可能です。顧客に安心・安全でおいしいご飯を届けることを通じて、価値を提供できるでしょう。 集客効果を高めるためには、「栄養士監修」「栄養士考案」などのキーワードを入れてアピールするのが重要です。
食堂
学生寮や会社の食堂で、栄養バランスの取れた食事を提供します。学生寮の場合は成長期に必要な栄養素が含まれていること、会社の場合は生活習慣病に配慮した健康的な食事を提供するのが重要です。 ここでは組織や企業に属して働くケースを紹介しましたが、実績や経験を積んで独立し、フードコーディネーターやセミナー講師などとしてフリーで活動する栄養士もいます。幅広い領域で活動できるのが、栄養士の特徴です。
栄養士の一日の流れ
栄養士の一日の流れを、介護老人保健施設に勤務する場合と、保育園に勤務する場合に分けて詳しく見ていきましょう。
介護老人保健施設に勤務の例
介護老人保健施設に勤務する栄養士の一日の流れは、以下を参考にしてみてください。
時刻 | 勤務内容 |
8:00〜 | 前日に洗った食器やトレー、朝食の片付けをする。 |
9:00〜 | 昼食の準備・配膳をする。利用者ごとの身体の状態に合わせて、細かく刻んだりとろみをつけたりする。 |
11:00〜 | 昼食を提供する。 |
12:00〜 | 昼食の片付けをする。 おやつの準備をする。 必要に応じて、食材の発注をする。 |
13:00〜 | 昼食(昼休憩) |
14:00〜 | おやつを提供する。 |
15:00〜 | 夕食の準備・配膳をする。 |
17:00〜 | 退勤する。 |
介護老人保健施設はシフト制で勤務時間が異なることも多く、柔軟に働ける点がメリットです。
保育園に勤務の例
保育園に勤務する栄養士の一日の流れは、以下のようなイメージです。
時刻 | 勤務内容 |
8:00〜 | 朝に出す軽食を準備する。 |
9:00〜 | 昼食の仕込み・調理を始める。 子どもによってはアレルギーがあったり、離乳食の時期だったりするので調整する。 |
11:00〜 | 子どもたちに提供する昼食を盛り付ける。 提供前に、問題がないかを確かめるための検食を行う。 |
12:00〜 | 子どもたちと一緒にお昼休憩に入る。 |
| 13:00~ | 昼食の片付けをする。 おやつの準備を始める。 |
15:00〜 | おやつを提供する。 |
16:00〜 | 食材発注・献立作成などの事務作業をする。 施設によっては、夕食や補食を作る場合もある。 |
17:00〜 | 退勤する。 |
栄養士の魅力・やりがい
栄養士の魅力・やりがいは、なんといっても食を通して人々の健康をサポートできる点です。
学校給食の現場では成長期の子どもに必要な食事を届ける、社員食堂では生活習慣病を予防するための食事を提供する、病院では機能回復や健康的な生活を目指して献立を立てる、などといった関わり方ができます。
また食品メーカーや飲食店で働くと、より多くの人に食品・食事を届けられます。自分が作ったメニューや商品が採用される喜びは、他の何にも代えがたい達成感を味わえるでしょう。
栄養士に向いている人の特徴
栄養士に向いている人の特徴には、以下が挙げられます。
- 食や栄養に関して興味がある
- 料理をするのが好き
- 人とコミュニケーションを取ることが好き
- 創意工夫が好き
もちろん上記の全てに当てはまっている必要はありません。どれか一つでも当てはまるなら、栄養士としての素質はあるでしょう。
栄養士になる方法
栄養士になるには、厚生労働大臣が指定する栄養士養成施設で、2年以上の専門課程を修了する必要があります。2年または3年制の専門学校・短期大学、4年制の大学などで専門課程を学ぶことが可能です。
栄養士養成施設では、以下に挙げる内容について学びます。
- 生理学・解剖学・生化学
- 公衆衛生学・医学概論
- 食品学
- 栄養学
- 調理学
- 食品加工学
- 食品衛生学
- 食品とアレルギー
- 子どもと食育
栄養士になるための学校を選ぶ際は、得た知識をスムーズに実務に生かせるよう、座学だけではなく演習や実習が充実しているところがおすすめです。
管理栄養士へのステップアップも可能
より高度な知識が求められる管理栄養士になり、キャリアアップを目指すことも可能です。国家試験を受験するには、以下の受験資格を満たしている必要があります。
●2年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士の資格を得た者:3年以上の実務経験を経ること
●3年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士の資格を得た者:2年以上の実務経験を経ること
●4年制の栄養士養成施設を卒業して栄養士の資格を得た者:1年以上の実務経験を経ること
●4年制の管理栄養士養成施設を卒業して規定の期間までに栄養士の免許を受けること
管理栄養士国家試験では、以下の内容が問われます。
- 社会・環境と健康
- 人体の構造と機能および疾病の成り立ち
- 食べ物と健康
- 基礎栄養学
- 応用栄養学
- 栄養教育論
- 臨床栄養学
- 公衆栄養学
- 給食経営管理論
管理栄養士になると、健康な人のみならず傷病者を対象に、症状や体調を考慮した栄養指導や食事管理を行えるようになります。
※参考:厚生労働省.「管理栄養士国家試験」.
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/ ,(参照 2024-01-15).
栄養士の平均年収
栄養士を目指す上で気になるのが、その平均年収です。<
厚生労働省が公表した「賃金構造基本統計調査」によると、2023年の栄養士の平均月収は26.8万円、年間賞与やその他の特別支給額は68.4万円です。これらを元に計算すると、平均年収は390万円となります。
国税庁の調査「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均給与は460万円です。 これと比較するとやや少ない水準ですが、実績や経験を積んだり、管理栄養士へとキャリアアップすることで、年収アップが期待できます。
※参考:e-Stat 政府統計の総合窓口.「賃金構造基本統計調査 」.
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003426315 ,(参照 2025-01-14).
※参考:国税庁.「令和5年分 民間給与実態統計調査」.
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2023.htm ,(参照 2025-01-14).
栄養士の将来性
栄養士の将来性は、以下の点で高まるとされています。
- 健康意識の高まり
- 高齢化の加速
- 食育の推進
栄養士の将来性が高い理由としてまず挙げられるのが、健康意識が高まっている点です。人生100年時代と呼ばれる昨今、生活習慣病やメタボリックシンドロームを予防するために、栄養士は食の知識を通じて人々の健康をサポートできます。
また日本では、今後さらに高齢化が加速する点も理由の一つです。低栄養や嚥下障害など、高齢者特有の栄養課題に対応していくためには、栄養士の知識と経験が求められます。
さらに、食育基本法が制定されたことを背景に食育が推進されている点も、将来性に期待できる理由です。子どもから大人まで、幅広い世代に対して正しい食の知識を普及する役割を担います。
まとめ
栄養士は食事や栄養に関する指導や管理を行う、栄養学のスペシャリストです。学校や病院、食品メーカーなどで栄養指導や栄養管理、食育などの業務を行います。
食を通じて人々の健康をサポートできる点や、商品開発を通じてより多くの人に食品・商品を提供できる点などが魅力です。健康意識の高まりや食育の普及などにより、今後はさらに栄養士の需要は高まると予想されています。興味のある方は、ぜひ目指してみましょう。
仙台青葉学院短期大学の栄養学科では、2年間の教育課程で栄養に携わる人としての専門的知識や技術、責任と自覚を学べます。個々のライフステージを考えながら豊かな生活をサポートできる栄養士になるための専門課程、演習、実習、実験などのカリキュラムを用意しており、実践力を身につけることができます。
また、キャリアアップを目指す卒業生を対象とした管理栄養士国家試験対策講座もあり、卒業後でも講義を受講できます。
栄養士の他に、社会福祉主事任用資格や食品衛生責任者の資格の取得もできます。栄養士を目指している方は仙台青葉学院短期大学に、ぜひお問い合わせください。